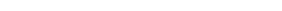気候変動への対応 ~TCFD 提言に基づく取り組み・カーボンニュートラルへの挑戦~
日本パーカライジングは、2024年1月にTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言への賛同を表明するとともに、同提言に賛同する企業・金融機関等により構成されるTCFDコンソーシアムへ参画いたしました。TCFDフレームワークに基づいた情報開示を通して、ステークホルダーの皆さまに気候変動対応状況について説明責任を果たします。また、気候変動のシナリオ分析で特定したリスクおよび機会から評価した事業インパクトと財務への影響に応じて、適切な対応策を講じてまいります。


ガバナンス
持続可能な社会の実現に向けて、企業に対する社会からの要請や期待が高まる中、当社は経営理念に基づき、持続的な成長を目指すとともに、経済的価値と社会的価値の両立を図っています。気候変動をはじめとするサステナビリティ課題への対応を一層強化するため、2023年7月にサステナビリティ委員会を設置しました。
本委員会は年4回開催され、以下の事項について審議を行います。
・TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)に基づくシナリオ分析結果
・気候関連課題への対応策
・サステナビリティに関する定性的・定量的目標の設定と進捗状況
これらの審議内容は、委員会から執行役員会および取締役会へ年1回以上、適時報告されます。取締役会は、サステナビリティ活動全体を監督し、企業としての責任ある対応を推進しています。
サステナビリティ委員会の開催実績:2024年8月、2025年1月、4月、6月
戦略
短期・中期・長期の時間的観点を踏まえ、気候変動がバリューチェーンにもたらす政策・規制や市場変化などによる移行リスク、異常気象などの物理リスクの中で、特に事業への影響が大きいと想定されるリスクと機会を当社が定めるリスクと機会の評価プロセスに従って、評価・特定しました。さらに気候変動という課題が持つ特性から長期の時間的視点において、2030年時点における当社のビジネス環境がどのように変化しうるのかについてもシナリオ分析を実施しています。シナリオ分析では、国際エネルギー機関(IEA)や気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が公表する複数の既存シナリオを参照の上、脱炭素への移行が加速する「1.5℃未満シナリオ」「2℃未満シナリオ」と最も気温が上昇する「4℃シナリオ」の3パターンを想定しました。事業への影響が大きいと想定されるリスクと機会を下記のとおり特定し、2030年における財務影響を可能な限り定量化しました。
※参考シナリオ 移行リスクIEA NZE, IEA APS, IEA STEPS 物理リスクSSP1-1.9, SSP1-2.6, SSP5-8.5
シナリオ分析
1.5℃未満シナリオ
| 分類 | 内容 | 時間軸 | 影響度 | 対応策/取組み | |
|---|---|---|---|---|---|
| リスク | 政策・法規制 | 炭素税導入、排出規制強化 | 中~長期 | 中 | 省エネ推進 再エネ導入/グループ含め推進中 太陽光発電/検討中 |
| 原材料調達 | 環境規制による調達困難 | 中~長期 | 中 | 複数購買の推進/複数購買化 | |
| 市場変化 | 顧客からの脱炭素要請 | 中~長期 | 大 | 環境対応製品の開発 CFP算定/案件毎対応 |
|
| 技術対応 | 顧客の技術革新への対応 | 中~長期 | 大 | 技術開発と顧客連携の強化 | |
| 自然災害増加 | 希少資源の調達困難 | 短~長期 | 小 | サプライヤーエンゲージメントの強化 複数購買の推進 |
|
| 機会 | 製品・サービス | 環境対応製品の需要増 | 中~長期 | 大 | 新製品開発 カスタマイズ対応 |
| 新市場 | 脱炭素市場の拡大 | 中~長期 | 大 | 新分野開拓 | |
4℃シナリオ
| 分類 | 内容 | 時間軸 | 影響度 | 対応策 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リスク | 自然災害 | 台風・洪水などによる操業停止 | 中~長期 | 小〜中 | BCP強化 拠点分散 災害対応訓練 |
| 原材料 | 希少資源の供給不安 | 中~長期 | 小〜中 | 調達先多様化 代替素材の研究 |
|
| 機会 | 防災関連 | 災害対応技術・製品の需要増 | 中~長期 | 中 | 防災インフラ向け製品開発 |
| レジリエンス | サプライチェーン強化の需要 | 中~長期 | 中 | 安定供給体制の構築支援 | |
1.5℃未満シナリオに基づく重要な戦略
戦略1
脱炭素に対する対応
事業活動にともなうCO2排出量は、対策を講じなければ事業成長とともに増加が見込まれ、炭素税導入時には数億円規模の営業利益への影響が懸念されます。このリスクに対応するため、2030年までに売上高原単位でCO2排出量(Scope 1・2)を2020年度比で30%削減する目標を設定しました。加えて、グループ全体で省エネ活動の推進を検討中です。
戦略2
原材料調達リスクへの対応
環境規制などにより新たな原材料の調達が必要となる可能性があり、調達困難時には十数億円規模の営業利益への影響が懸念されます。このリスクに対応するため、重要課題として「持続可能な社会の実現に向けた責任ある対応」を掲げ、サプライヤーとの協働による安定供給体制の構築に加え、代替原材料の活用と製品への切り替えを推進しています。
戦略3
脱炭素への取り組み
脱炭素への要請が高まる中、対応が不十分な場合には受注減による数十億円規模の営業利益損失が懸念されます。 このリスクに対応するため、マテリアリティとして「SDGsを意識した製品・技術の開発」を掲げ、お客さまの製造工程における環境負荷低減を支援します。さらに、製品・サービスごとにCFP(カーボンフットプリント)を算定しCO2排出量を“見える化”することで、脱炭素社会の実現に貢献しています。
戦略4
新規市場への対応
カーボンニュートラルの流れが世界的に加速する中、脱炭素市場では革新的技術の開発と製品ニーズが急速に拡大しています。当社は、マテリアリティとして「表面改質技術による豊かな社会の創出」を掲げ、長年培った独自技術を 生かして新規市場向けの製品展開を積極的に推進しています。
リスク管理
気候関連リスクの管理体制
当社では、気候関連リスクの特定・評価はサステナビリティ委員会が、その他の事業リスクはリスク管理委員会が担っています。サステナビリティ委員会では、TCFD提言に基づくシナリオ分析を通じて重要なリスクと機会を特定し、影響度を評価。リスクは「影響度(営業利益基準)」と「発生可能性(頻度)」をそれぞれ4段階で評価し、総合的に16段階で重要度を判定。これにより、リスク間の相対関係を踏まえた優先順位づけと対応策の決定を行っています。
気候関連リスクの管理プロセス
当社では、事業リスクに対して重要性に基づく対応策の立案・実行・管理・改善を行っています。気候関連の移行リスクや機会については、環境戦略に反映し、目標・計画に落とし込んだ上でPDCAサイクルを回し、環境パフォーマンスとリスク管理の向上を図っています。
総合的リスク管理との統合
当社グループでは、事業目標の達成を阻害するリスクを効果的に管理するため、リスク管理委員会を設置し、経営リスクを中心に評価・対応策を検討し、内部統制委員会へ報告しています。気候変動リスクについてはサステナビリティ委員会が主体となって対応しており、両委員会は全社的なリスクマネジメント活動において緊密に連携・協力しています。
指標と目標
日本パーカライジングは、2020年度比でGHG排出量(Scope 1+2)を2030年度までに30%削減する目標を掲げています。2025年3月期の当社単体のGHG排出量を算定した結果、再生可能エネルギーの導入や省エネ活動の推進などにより、目標を上回る33%の削減を達成しました。今後は、国内外の連結子会社も含めた削減目標を設定し、グループ全体でカーボンニュートラルの実現を目指します。
Scope1,2,3のGHG排出量
開示しているGHG(温室効果ガス)排出量の透明性と信頼性を保証するため、第三者の外部機関(ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社)による検証を受けています。